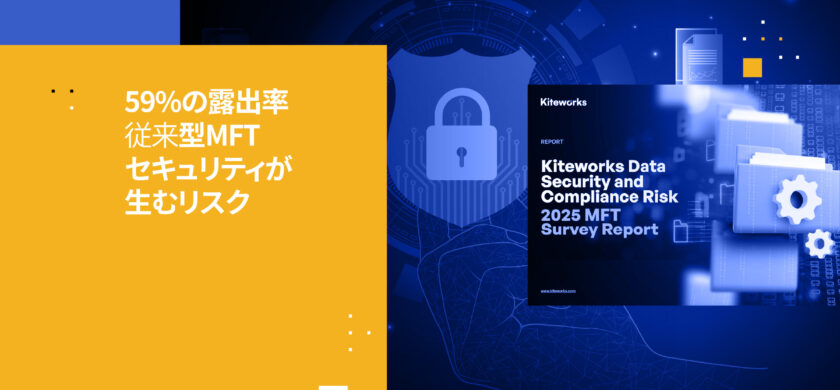
59%の露出率:従来型MFTセキュリティが生むリスク
多くの組織はサイバーセキュリティに数百万ドルを投資しています。ファイアウォール、エンドポイント保護、セキュリティオペレーションセンターなど、標準的な防御策はすべて導入済みです。コンプライアンスチームも着実にチェックリストをこなしています。しかし、Kiteworksの初となるデータセキュリティとコンプライアンスリスク:MFT調査レポートによると、過去1年で59%の組織がマネージドファイル転送のセキュリティインシデントを経験しています。IBMの2025年データ侵害コストレポートによれば、データ侵害による平均損失額は世界で4.44百万ドル(米国では10.22百万ドル)にのぼり、これらは単なる統計ではなく、ビジネス存続を脅かす現実のリスクです。
不都合な現実として、組織が境界防御を強化する一方で、攻撃者はファイル転送システムを巧妙に突いてきます。政府機関では保存ファイルデータの暗号化率がわずか8%。医療機関でも11%しか保護されていません。資金力のある中堅企業は侵害率が32%と最も高くなっています。これらはゼロデイ脆弱性を突く高度な国家レベルの攻撃ではなく、日々組織の最も機密性の高いデータを扱うシステムにおける基本的なセキュリティの不備が原因です。
マネージドファイル転送(MFT)システムは、周辺的なITインフラではありません。知的財産、顧客データ、財務記録、競争インテリジェンスといった重要情報を運ぶ「幹線道路」です。これらのシステムが失敗すれば、その影響は組織全体に波及します。調査データは、多くの企業がこの重要なシステムを最小限の可視性、分断されたアーキテクチャ、不十分な管理体制で運用していることを明らかにしています。
MFTの死角―誰も語らないリスク
多くの組織が直面しているアーキテクチャの現実は、どんなセキュリティ専門家も驚かせる内容です。調査によると、62%の企業がメールセキュリティ、ファイル共有、Webフォームなどで分断されたシステムを運用しています。これは単なる効率性の問題ではなく、各システムが新たな攻撃経路や認証管理の課題、ログの抜け穴を生み出し、攻撃者に悪用されています。
医療機関はこの危険な分断の典型です。データ転送時のエンドツーエンド暗号化を100%実現している一方で、保存データの暗号化はわずか11%。この可視化されたセキュリティ対策と実際の保護とのギャップが、誤った安心感を生み、結果的に高いコストを招いています。インシデント率44%、侵害率11%(全業界で最高水準)は、コンプライアンスのチェックリストがセキュリティそのものを意味しないことを示しています。
手作業によるプロセスの問題も、こうしたアーキテクチャ上の弱点をさらに悪化させます。自動化が進んだ現代でも、87%の組織はMFTシステムを通じたファイル転送の自動化率が90%未満。重要なワークフローがいまだ手作業に依存しており、人的ミスのリスクが拡大しています。手動転送の一つひとつが、ポリシー違反や監査ギャップ、セキュリティインシデントの温床となっています。
さらに深刻なのが、セキュリティ監視の分断です。調査では、63%の組織がMFTシステムをセキュリティ情報イベント管理(SIEM)やセキュリティオペレーションセンター(SOC)と連携していません。ネットワークやエンドポイント、アプリケーションの監視は高度に行われている一方で、最も機密性の高いデータがやり取りされるファイル転送は「暗闇」の中で運用されています。セキュリティチームは「王冠の宝石」を動かすシステムだけを見逃しているのです。
この可視性のギャップは、相関関係の盲点を生み出します。攻撃者が認証情報を侵害した場合、まずファイル転送を通じてアクセスをテストし、その後大規模な攻撃に移行することが多いのです。MFTイベントがセキュリティデータレイクに記録されなければ、こうした初期の警告サインは見逃されます。インサイダー脅威が関与するインシデント(27%)は、ファイル転送の活動がセキュリティチームから見えない場合、特に危険性が高まります。
主なポイント
-
暗号化ギャップが最大の脆弱性を生む
多くの組織は転送中データの保護に注力する一方、保存データを軽視しています。76%が転送時の暗号化を実施しているのに対し、保存ファイルをAES-256で保護しているのはわずか42%。この34ポイントのギャップにより、攻撃者は厳重に守られた幹線道路を避け、何年分もの機密ファイルが無防備に蓄積された倉庫を狙うのです。
-
セキュリティチームは「見えないもの」を守れない
63%の組織がSIEM/SOCと連携せずにMFTシステムを運用しているため、セキュリティチームは最も機密性の高いデータの実際の動きを監視できていません。この可視性のギャップにより、ファイル転送はブラックボックス化し、インサイダー脅威(インシデントの27%)や初期の攻撃兆候が被害発生まで完全に見逃されます。
-
規模やコンプライアンスだけではセキュリティは担保できない
中堅企業(従業員5,000~10,000人)は、リソースや定期的なテストを行っているにもかかわらず、侵害率が32%と最も高く、政府機関も厳格なコンプライアンス枠組みがありながら保存データの暗号化率は8%にとどまっています。データは、セキュリティ成果が組織規模や規制要件ではなく、実装品質に左右されることを証明しています。
-
分断はリスクを指数関数的に増大させる
メールセキュリティ、ファイル共有、Webフォームなどで分断されたシステムを運用する62%の組織は、単にリソースを浪費するだけでなく、システム間のポリシー不一致や監視の抜け穴を生み出し、攻撃者に悪用されるギャップを作り出しています。統合プラットフォームではインシデントが50%少なくなり、アーキテクチャのシンプルさが機能の多様性を上回ることが証明されています。
-
自動化は効率化だけでなく、セキュリティ対策そのもの
MFT自動化率が90~100%の組織は、29%のインシデント率にとどまり、50%未満の組織では71%に達しています。手動ファイル転送のたびにポリシー違反や人的ミスのリスクが増大し、侵害につながるため、自動化の推進は運用効率化以上に重要なセキュリティ投資です。
セキュリティ成果を左右する3つの重大なギャップ
調査データは、インシデントを経験した59%とセキュリティを維持した39%を分ける3つの具体的な脆弱性を特定しています。これらは複雑な技術課題ではなく、組織が集中して取り組めば解消できる基本的なギャップです。
ギャップ1:暗号化のアンバランス
暗号化データは、優先順位の誤りを物語っています。76%の組織が転送中データのエンドツーエンド暗号化を実施している一方で、保存データにAES-256暗号化を使用しているのは42%のみ。この34ポイントのギャップにより、何百万ものファイルがストレージやバックアップ、一時ディレクトリに無防備なまま放置されています。
政府機関は、このアンバランスの極端な例で、保存データの適切な暗号化を実施しているのはわずか8%と、全業界で最低水準です。インシデント率58%、不正アクセス試行率42%という結果は、この根本的な弱点と直結しています。皮肉なことに、これらの機関は最も厳格なポリシー要件やコンプライアンス枠組みを持っているのです。
なぜこのギャップが放置されるのでしょうか。多くの組織は、暗号化をコンプライアンスの「チェックボックス」として捉え、セキュリティ対策としての本質を見失っています。TLSなど転送時の可視化しやすい対策は導入しても、攻撃者の主な標的が保存データである現実を無視しているのです。転送中データへの攻撃には高度な中間者攻撃が必要ですが、暗号化されていない保存ファイルへのアクセスは、基本的なシステム侵害だけで十分です。
この問題の解決に大規模なアーキテクチャ変更は不要です。転送時暗号化を導入している組織の多くは、数週間で保存データにも暗号化を拡張できます。最新のMFTプラットフォームでは、保存時暗号化は設定オプションとして用意されており、複雑な導入プロジェクトを必要としません。最大の障壁は技術的な難しさではなく、認識と優先順位付けの問題です。
ギャップ2:統合の欠如
MFTシステムを広範なセキュリティ監視基盤と連携している組織はわずか37%。つまり63%は、セキュリティ可視性に巨大な死角を抱えたまま運用しています。ファイル転送が行われ、機密データが移動し、潜在的な侵害が発生しても、組織を守るSOCチームにはまったく見えません。
この統合ギャップは、インシデントの傾向を考慮すると特に高くつきます。調査によれば、インシデントの27%は不正アクセスが関与しており、その多くはインサイダーの認証情報が侵害されたケースです。こうした攻撃は小規模なファイルダウンロードから始まり、徐々に拡大します。MFTイベントがSIEMに流れなければ、こうした重要な初期兆候は見逃されます。
最新のMFTプラットフォームには、SIEMコネクタが標準搭載されています。統合には数時間しかかからないのが一般的です。しかし、依然として多くの組織がMFTを運用システムとみなし、セキュリティの中核コンポーネントとして扱っていません。統合していない63%は、セキュリティプログラムを「片目を閉じて」運用しているのと同じです。
この盲点の複合的な影響は、攻撃の見逃しだけにとどまりません。コンプライアンス監査はログ収集の手作業作業となり、インシデント対応チームは調査時に重要な文脈を欠き、セキュリティアナリストはファイル転送の正常な行動パターンを構築できません。これらのギャップが、リスクと運用コストの両方を増大させます。
ギャップ3:複雑性の重荷
メールセキュリティ、ファイル共有、Webフォームなどで分断されたシステムを維持している62%の組織は、隠れた「複雑性税」を支払っています。システムが増えるごとにコストが増すだけでなく、ポリシーの不一致、システム間のギャップ、攻撃対象領域の拡大によってリスクが指数関数的に増大します。調査データは、統合プラットフォームの方が分断型よりもインシデントが約50%少ないことを明確に示しています。
この分断は、戦略的判断というよりも、個別ニーズへの場当たり的な対応から生じることが多いのが実情です。組織は特定用途ごとにポイントソリューションを追加し、累積的なセキュリティ影響を考慮しません。メールセキュリティには独自のポリシー、ファイル共有には別のポリシー、Webフォームにもまた別のルール。ユーザーは複数のインターフェースと認証情報を使い分け、ITチームは個別設定を維持し、セキュリティチームは分断されたシステムを監視します。
実際のコストはインシデントデータに現れます。分断型組織は一貫したポリシー適用が困難です。たとえば、機密データのメール送信がブロックされても、ファイル共有システム経由でアップロードできてしまう場合があります。あるシステムでアクセス権を剥奪しても、別のシステムでは残ったまま。こうした不整合が攻撃者に悪用されるギャップとなります。
プラットフォーム統合には通常12~18カ月かかりますが、セキュリティ向上と運用効率化の両面でROIをもたらします。統合プラットフォームを運用する38%の組織は、インシデントが減るだけでなく、総所有コストの削減、コンプライアンスの簡素化、ユーザー体験の向上も実現しています。統合への投資は、侵害の回避と運用負担の軽減という形で確実に回収できます。
業界別分析:成功と失敗のパターン
調査データは、業界ごとに明確な傾向を示し、セキュリティ成熟度に関する一般的な思い込みを覆しています。規模が大きければ安全というわけではなく、コンプライアンス枠組みがあっても保護は保証されません。高度な組織でさえ、根本的なギャップを抱えています。
政府機関:枠組みはあっても基盤がない
政府機関は、ポリシーと実践の乖離が最も顕著な例です。これらの組織は通常、NISTやFedRAMPなど、最も厳格な枠組みや連邦規制下で運用されています。データ主権要件の適用率は67%と全業界で最高ですが、保存データの暗号化率は8%と最低水準です。
枠組みの導入と技術的実装のギャップが、インシデント率58%という結果を招いています。不正アクセス試行率42%は、攻撃者がどこを狙うべきかを熟知している現実を反映しています。政府システムは境界防御は強固でも、内部統制が弱いことが多いのです。接続が暗号化されていても、到達先でデータが無防備なら意味がありません。
根本原因は、成果よりも機能を重視する調達プロセス、基盤的なセキュリティよりも目に見える施策に予算を割くサイクル、ポリシーと実装が分断された組織構造など、深い部分にあります。強固な枠組みと弱い技術的管理策のギャップを埋めない限り、高いインシデント率は続くでしょう。
医療機関:コンプライアンスはあってもセキュリティは不十分
医療機関は、転送中データのエンドツーエンド暗号化を100%導入するという驚異的な成果を上げています。他業界では類を見ない普及率です。しかし、同時に保存データの保護はわずか11%にとどまり、危険なセキュリティギャップがインシデント率44%という結果に直結しています。
このパラドックスは、HIPAAの「暗号化は必須ではなくアドレス可能」とする構造にも一因があります。組織はこの柔軟性を「目に見える対策だけで十分」と解釈し、根本的な保護を後回しにしているのです。その結果、患者データはシステム間の転送時には安全でも、保存時には無防備となり、侵害の大半がここで発生します。
医療業界の分断も脆弱性を増幅させます。臨床システム、管理プラットフォーム、研究データベース、パートナー連携など、複雑なエコシステムの中で一貫したセキュリティの実現は困難です。各システムは個別にコンプライアンス要件を満たしていても、全体としては巨大な脆弱性を生み出しています。侵害率11%(全業界で最高水準)は、チェックボックス的なセキュリティの本当のコストを示しています。
金融サービス:バランスの取れた実装が効果を発揮
金融サービス業界は、実践的なセキュリティの好例です。インシデント率25%(調査平均の半分)、侵害率8%と、バランスの取れた実装が成果を上げています。特定の管理策で突出しているわけではありませんが、すべての重要分野で堅実な導入率を維持しています。
最大の違いは、「卓越性」よりも「一貫性」を重視している点です。金融サービス組織は、転送・保存時の暗号化、アクセスガバナンス、ベンダー評価、監視統合など、全体的に中~高水準の実装を見せています。高度な機能を追い求めるあまり、基本的なギャップを放置することがありません。
このバランスの取れたアプローチは、成熟したリスク管理文化や規制監査経験に根ざしています。個別のコンプライアンス枠組みごとに対策を分けるのではなく、複数要件を同時にカバーする統合的な管理策を構築しています。その結果、実際に機能するセキュリティを実現しています。
中堅企業:危険地帯
調査で最も懸念されるのは、従業員5,001~10,000人規模の中堅企業です。インシデント対応計画のテスト率が75%と高いにもかかわらず、侵害率は32%と全規模で最悪。このパラドックスは、規模が大きくなることで高度な攻撃者の標的となり、防御体制が成熟する前に攻撃が集中する「危険な移行期」にあることを示しています。
これらの組織は、価値あるデータを扱い、執拗な攻撃者を引き付ける規模に達していますが、大企業のような成熟したセキュリティ基盤はまだ整っていません。高度な機能を導入しつつ、基本的なギャップを埋めきれていない状況です。この組み合わせが、セキュリティ失敗の温床となっています。
高いテスト率と悪い成果の組み合わせは、プロセス重視で実効性が伴っていないことを示唆しています。実際の脆弱性に対応しない計画をテストしても、現実の攻撃には対応できません。本当のセキュリティには、単なるテストだけでなく、正しいシナリオの検証と、そのギャップへの対応が不可欠です。
自動化の現実
自動化は、調査データで最も明確にセキュリティ成果と相関する要素の一つです。MFTを使ったファイル転送の自動化率が90~100%の組織は、インシデント率が29%と、50%未満の組織(71%)の半分以下です。しかし、高い自動化レベルに到達しているのはわずか13%で、大多数は50~70%の間で停滞しています。
50~70%の停滞
自動化の停滞は、技術的な限界よりも組織的な要因を反映しています。50~70%の自動化を達成した企業は、通常、定期転送や標準ワークフロー、一般的な連携など、最も簡単なユースケースを自動化済みです。残る30~50%は、複雑なプロセスや例外処理、複数システムにまたがるワークフローが含まれます。
多くの組織はこの段階で「ほとんど自動化できた」と満足し、さらなる投資の効果が薄いと考えます。しかし、この視点は、残された手動プロセスが持つセキュリティ上の影響を見逃しています。手動処理の30%には、最も機密性が高く複雑なシナリオが含まれることが多く、まさにセキュリティが最も重要となる領域です。
調査は、自動化率が上がるごとに明確なセキュリティ改善が得られることを示しています。50~69%から70~89%への移行でインシデントが9ポイント減少し、90~100%へのジャンプでさらに23ポイント改善します。これらは些細な向上ではなく、運用の徹底によって得られる大きなセキュリティ変革です。
自動化の壁を突破する
自動化の停滞に直面する組織は、技術的な障壁よりも文化的な障壁に悩まされていることが多いです。ビジネスユーザーは慣れ親しんだ手作業プロセスの変更に抵抗し、ITチームは複雑な連携プロジェクトのリソースが不足し、セキュリティチームは自動化をセキュリティ対策と認識していません。こうした人的要因の方が、技術要件よりも克服が難しいのです。
成功している組織は、自動化を効率化ではなく「セキュリティの必須要件」として位置付けています。まずは機密データを扱う、またはミスが起きやすい高リスクの手動プロセスから着手し、セキュリティと運用両面のメリットを示す「クイックウィン」で勢いをつけます。成果は単なる時間短縮ではなく、リスク削減で測定します。
停滞を打破するには、異なるアプローチが必要です。異種システムをつなぐオーケストレーションプラットフォーム、整合性を担保するインフラストラクチャ・アズ・コード、手動プロセスを例外とし自動化を標準とする文化変革などです。自動化率90~100%を達成した13%の組織は、技術だけでなく、文化的な変革によってこの水準に到達しています。
現代の脅威には現代的な防御が必要
従来型のセキュリティ対策は、現代のファイルベース攻撃にはもはや通用しません。調査によると、コンテンツ無害化と再構築(CDR)技術を導入している組織はわずか27%で、大多数が従来型防御をすり抜ける高度な脅威にさらされています。
コンテンツセキュリティのギャップ
標準的なアンチウイルスやデータ損失防止(DLP)ツールは、63%の組織で導入されており、既知の脅威や明白なデータ漏洩には対応できます。しかし、一般的なファイル形式に埋め込まれたゼロデイ攻撃には無力です。武器化されたPDFや悪意あるOffice文書、改ざん画像は、従来のスキャナーをすり抜けてしまいます。これらのファイルは既知のマルウェアシグネチャを含まず、正規機能を悪用するためです。
CDR技術は、すべてのファイルを潜在的に危険と見なし、脅威の検出ではなく、ファイルを再構築して悪意あるコンテンツを除去し、ユーザーに必要な正規情報だけを残します。特に外部(ベンダー、顧客、パートナー)からのファイルを扱う組織にとって、このアプローチは非常に有効です。
導入率が27%と低いのは、認知不足と運用面の課題が主因です。CDRは一部のファイル機能がセキュリティのために除去されることを受け入れる必要があり、ユーザーもその理由を理解しなければなりません。こうしたチェンジマネジメントの課題が、技術的な複雑さやコスト以上に普及を妨げています。
ベンダー評価の「見せかけ」
調査で最も顕著なギャップは、ベンダーセキュリティ評価に関するものです。72%の組織が「徹底的に」ベンダーセキュリティを評価していると回答する一方、インシデント率は59%と高止まりしており、評価が本質的な脆弱性を見逃していることが明らかです。評価と実際のセキュリティ成果のギャップは、サードパーティリスクへのアプローチに根本的な問題があることを示しています。
従来のベンダー評価は、ポリシーや認証、アンケート回答に重点を置きます。ベンダーは営業時に最良の面をアピールし、機能や実績、コンプライアンスを強調します。しかし、実際の運用でしか見えないアーキテクチャ上の弱点や統合ギャップ、運用上のセキュリティ不備は明らかにされません。
本当のベンダーセキュリティ評価には、より深い調査が必要です。プラットフォームは暗号鍵をどう扱うのか、データ処理時に何が起きるのか、統合がセキュリティモデルにどう影響するのか、現行顧客の実際のセキュリティ成果を示せるのか。こうした難しい質問こそが、見せかけのセキュリティと実質的な保護を分けるポイントです。
実装の現実:重大なギャップからセキュリティへ
調査データは、実証済みの効果に基づく具体的なアクションプランを可能にします。完璧を目指すのではなく、最も重要なギャップを体系的に解消することで、実質的なセキュリティ向上が実現できます。
最大の脆弱性から着手する
多くの組織にとって、最も効果的なアクションは保存データへのAES-256暗号化の導入です。58%が保存データの適切な暗号化を欠いており、76%がすでにエンドツーエンド暗号化を実装している現状では、ここが最大のリスクです。保存時暗号化がないままでは、何年分ものファイルが日々さらされ続けます。最新のMFTプラットフォームなら、これは設定変更だけで即時対応でき、暗号鍵がなければ攻撃者にとって保存データは無価値となります。
次に、MFTログをSIEMに連携して可視性を確保しましょう。統合していない63%の組織は、重要な攻撃兆候を見逃しています。初期導入では複雑な相関ルールは不要で、まずはファイル転送イベントをセキュリティデータレイクに流すだけで、調査やパターン認識が可能になります。最新のMFTプラットフォームには、数時間で有効化できるSIEMコネクタが用意されています。
基礎的なセキュリティ対策の仕上げとして、アクセス権の監査を実施しましょう。調査では、インシデントの27%がインサイダー脅威に関与しており、多くは無効化されるべき認証情報の放置が原因です。休眠アカウントや過剰な権限、共有認証情報を特定し、不要なアクセスは積極的に削除してください。この管理作業は時間以外のコストがかからず、即座に攻撃対象領域を減らせます。
これらは大きな変革ではなく、多くの組織が高度な機能を追い求めるあまり見落としがちな、基本的なセキュリティ衛生です。しかし、即効性のあるリスク低減効果をもたらします。
持続可能なセキュリティの構築
クイックウィンの先には、自動化とガバナンスによる持続的なセキュリティが必要です。退職者のファイル転送アクセスを即時剥奪する自動化を導入しましょう。52%の組織がこの機能を持たず、元従業員が無期限にシステムへアクセスできる脆弱性を抱えています。
定期的なアクセス権レビューを実施していない42%の組織は、四半期ごとのレビューサイクルを確立してください。最新のMFTプラットフォームには、アクセスガバナンス機能が標準搭載されており、多くの作業を自動化できます。重要なのは、習慣化と継続性です。各レビューで、リスクを生む過剰な権限が明らかになります。
分断型システムを運用している組織は、統合計画を始めましょう。移行には12~18カ月かかりますが、計画段階でポリシーの整合や冗長システムの排除、連携ポイントの特定など、即効性のある改善点が見つかります。現状を正直に把握し、機能リストではなくセキュリティ成果を基準に目標アーキテクチャを設計してください。
成功指標は、コンプライアンスのチェックリストを超えたものにしましょう。ファイル転送異常の検知までの平均時間、自動化と手動転送の比率、退職者の完全なアクセス剥奪までの所要時間など、運用指標で実質的なセキュリティ向上を示せます。
高度な保護戦略
高度な機能に取り組む準備ができた組織は、CDR導入と自動化停滞の打破に注力しましょう。外部からのファイルや実行可能コンテンツ、重要システムへの転送など、リスクの高いファイル転送にCDRを導入します。まずはパイロット導入で変化管理を徹底し、リスク評価に基づいて段階的に拡大してください。
自動化率50~70%の停滞を突破するには、コンプライアンスデータ収集や監査ログ集約、インシデント対応トリガーなど、セキュリティに直結するワークフローの自動化を進めましょう。自動化範囲が広がるほど、人的ミスの排除や一貫したポリシー適用によるセキュリティ効果が複利的に高まります。
高度な保護の仕上げとして、SIEMで実際の相関ルールを構築しましょう。MFTデータをセキュリティ監視に流し込み、行動ベースラインの確立や異常検知を実現します。大量ダウンロードや異常なアクセスパターン、不審な宛先への転送など、インパクトの大きいシナリオに注力してください。これにより、単なる可視性が実践的なインテリジェンスへと進化します。
ベンダー評価時は、機能リストではなくアーキテクチャの意思決定に注目しましょう。統合プラットフォームは、寄せ集め型ソリューションよりも一貫したポリシー適用や監視の簡素化、優れた連携を実現します。暗号鍵の管理やデータ処理時の挙動、実際のセキュリティ成果を示せるかなど、難しい質問を投げかけてください。約束された機能ではなく、実証された成果を基準に選定しましょう。
悪循環を断ち切る:勝者と被害者を分けるもの
KiteworksのMFTレポートは明確なメッセージを発信しています。ファイル転送セキュリティの失敗は、複雑さではなく「無関心」が原因です。インシデントを回避している39%の組織は、特別なリソースを持っているわけでも、簡単な課題に直面しているわけでもありません。基本的な管理策を徹底しているだけで、他の組織は高度な機能を追い求めるあまり、根本的なギャップを放置しています。
安全な少数派と脆弱な多数派を分けるのは、3つのアクションです。第一に、保存データを暗号化すること。58%が保存時暗号化を欠き、最大のリスクを抱えています。第二に、セキュリティ監視を統合すること。SIEM連携のない63%は、攻撃に対して部分的に盲目のままです。第三に、プラットフォームを統合すること。分断型システムを運用する62%は、アーキテクチャの複雑さによってリスクを増大させています。
何もしないコストは日々積み重なります。暗号化されていないファイルが一つ増えるごとにリスクが蓄積し、監視のない日々は攻撃兆候を見逃し、システムが増えるほど攻撃者に悪用される複雑性が高まります。高度なセキュリティ施策を議論する一方で、基本的なファイル転送の脆弱性は攻撃者にとって「開かれた扉」のままです。
調査は、セキュリティ変革に完璧さや無限のリソースは不要であることを証明しています。重要な脆弱性に集中し、体系的にギャップを埋めることで、実質的なリスク低減が可能です。MFTセキュリティを改善できるかどうかは、データが「可能」と証明しています。問題は、59%の組織のようにインシデント対応を通じて学ぶ前に、行動できるかどうかです。
今すぐ始めましょう。詳細な調査結果や業界別インサイトをまとめた調査レポートをダウンロードし、自組織をベンチマークと比較してください。自社の重大なギャップを特定し、体系的に解消を始めましょう。脆弱な多数派と安全な少数派の違いは、能力ではなく「行動」です。あなたの組織はどちらのグループに入りますか?
よくある質問
最も重大な脆弱性は「暗号化ギャップ」です。76%の組織が転送中データを暗号化している一方で、保存データをAES-256などで適切に保護しているのは42%のみ。そのため、何百万ものファイルがストレージやバックアップ、一時ディレクトリで無防備にさらされ、攻撃者の主な標的となっています。政府機関は保存データの暗号化率が8%と最も低く、インシデント率58%と直結しています。
中堅企業は32%という高い侵害率に直面しています。これは、十分な規模で高度な攻撃者の標的となる一方、大企業のような成熟したセキュリティ基盤が整っていないためです。こうした企業は、手作業プロセスが複雑さに対応できず、エンタープライズレベルの自動化管理策も十分に導入されていない「危険な移行期」にあります。調査では、75%がインシデント対応テストを実施しているものの、実際のセキュリティ実装がリスクに追いついていないことが示されています。
MFT自動化率が90~100%の組織は、インシデント率が29%にとどまり、50%未満の組織では71%に達しています。自動化によりポリシーの一貫した適用が可能となり、ファイル処理における人的ミスが排除され、脅威への迅速な対応も実現します。自動化率が20%上がるごとに、セキュリティインシデントが約10%減少する傾向があり、手動処理が多いほど侵害リスクが高まります。
統合型MFTプラットフォームを導入した組織は、メールセキュリティ、ファイル共有、Webフォームなどで分断されたシステムを運用する組織に比べ、セキュリティインシデントが約50%少なくなっています。統合には通常12~18カ月かかりますが、侵害コストの削減、コンプライアンスの簡素化、運用効率の向上によって投資回収が可能です。分断型システムを維持する62%の組織は、ポリシーの不整合や監視の抜け穴によってリスクが指数関数的に増大しています。
コンテンツ無害化と再構築(CDR)技術は、ゼロデイ攻撃や武器化ファイルに有効であるにもかかわらず、導入率がわずか27%と低迷しています。CDRは、ファイルから潜在的な悪意あるコンテンツを除去し、正規データのみを残すため、ベンダーや顧客、パートナーからの外部ファイルを扱う組織に特に有効です。導入が進まない主な理由は、技術的な複雑さやコストではなく、認知不足とチェンジマネジメントの課題です。